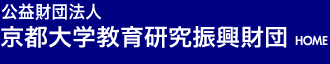令和7年度の助成採択者一覧
令和7年度の助成採択者一覧
今年度の採択者は以下の通りです。
| 教育・学術研究活動の推進に対する助成 | |
|---|---|
| 1. 研究活動推進支援 | |
| A. 研究活動推進助成 | |
| 2. 研究成果公開支援 | |
| B. 国際会議開催助成 | |
| 海外の学界との交流等、教育研究上の国際交流の促進に対する助成事業 | |
| 3. 研究者交流支援 | |
| C. 在外研究助成 | |
| D. 国際研究集会発表助成 | |
| 4. 国際交流支援 | |
| E. 国際交流助成 | |
| 社会との連携推進に対する助成事業 | |
| 5. 社会連携支援 | |
| F. 社会連携助成 | |
教育・学術研究活動の推進に対する助成
1. 研究活動推進支援
A. 研究活動推進助成
| 所属部局 | 職名 | 氏名 | 研究課題名 | 助成決定額 (円) |
成果 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育学研究科 | 助教 | 西山 慧 | 相補的学習システムに基づく記憶の再生モデルに関する実験・数理・計算論的検討 | 1,000,000 | |
| 法学研究科 | 教授 | 島田 裕子 | ケア労働の公正な分担と労働市場政策 | 1,000,000 | |
| 経済学研究科 | 教授 | 山田 憲 | 無形資本と生産性と雇用 | 1,000,000 | |
| 経済学研究科 | 講師 | 田所 篤 | 特恵貿易協定における輸入関税政策に関する新たな制度設計の指針 | 520,000 | |
| 人文科学研究所 | 教授 | 池田 巧 | 川西民族走廊の言語分布とその成立にかかる基層言語の解明 | 1,000,000 | |
| 人文科学研究所 | 特定准教授 | 森谷 理紗 | 音とイメージによる戦争体験の想起とアートを介した新しい歴史継承の実践的研究 | 1,000,000 | |
| 東南アジア地域研究研究所 | 准教授 | 山本 博之 | マラヤ・シンガポールにおける日本人の抑留・強制労働(1945-1947)とその政治的意味 | 1,000,000 | |
| 理学研究科 | 教授 | 日野 正訓 | 特異性を主題とする確率解析の展開 | 950,000 | |
| 理学研究科 | 教授 | 森 哲 | ヘビ類における特異的防御システムの進化:餌毒再利用メカニズムの洗練化過程の解明 | 1,000,000 | |
| 理学研究科 | 教授 | 上田 佳宏 | 超精密X線分光と多波長スペクトル分布から紐解く活動銀河核の構造と宇宙論的進化 | 1,000,000 | |
| 理学研究科 | 准教授 | 細川 隆史 | 極低金属の大質量星誕生:初代星の兆候発見に向けた理論的研究 | 1,000,000 | |
| 農学研究科 | 准教授 | 谷口 幸雄 | ダイズの根粒着生に関わる遺伝解析 | 1,000,000 | |
| 農学研究科 | 特定研究員 | 川原﨑聡子 | miRNAに着目した新規ベージュ脂肪細胞誘導能をもつ食品成分の探索 | 1,000,000 | |
| 地球環境学堂 | 准教授 | 吉見 啓 | 糸状菌の匂い応答メカニズムの総合理解 -揮発性分による物質生産制御を目指して- | 1,000,000 | |
| 化学研究所 | 助教 | 橋川 祥史 | 二開口型フラーレンをセグメントとする未踏ナノカーボンの創製 | 1,000,000 | |
| 高等研究院 | 特定助教 | 松木 久和 | 交替磁性体/超伝導体界面におけるクーパー対分裂効果によるキメラ準粒子の直接検出 | 1,000,000 | |
| ヒト行動進化研究センター | 助教 | 宮部 貴子 | 新規静脈麻酔薬レミマゾラムを用いたサル類の麻酔法の洗練 | 1,000,000 | |
| ヒト行動進化研究センター | 助教 | 桂 有加子 | 霊長類でのY染色体転座のメカニズムと2対の性染色体の機能・進化プロセスの解明 | 1,000,000 | |
| 工学研究科 | 教授 | 原田 英治 | RIM-PIVを用いた移動床環境における混相乱流構造の可視化と計測 | 1,000,000 | |
| 工学研究科 | 准教授 | 松田 俊 | 染色体定量プロテオミクスによる化学物質の遺伝毒性メカニズム特定法の開発 | 1,000,000 | |
| 工学研究科 | 助教 | 山田 諒 | アンボンドPCaPC部材のレジリエンス性能を考慮した合理的設計法の提案 | 1,000,000 | |
| 工学研究科 | 教授 | 髙田 滋 | 相変化とパターン形成に対する運動論的方法の開拓 | 1,000,000 | |
| 工学研究科 | 助教 | 畑田 直行 | 金属オキシ塩化物の熱力学量の網羅的解明に向けた新規測定技術 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 助教 | 長央 和也 | 臨床フェノタイピングに基づく心不全個別化診療の実現を目指した心不全コホートの構築 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 医員 | 北本 博規 | 慢性炎症環境下の体内鉄動態異常の是正に基づく炎症性腸疾患の新規治療開発 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 助教 | 山内 一郎 | TSH受容体シグナルの包括的理解に基づく甲状腺疾患の創薬基盤構築 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 助教 | 南 卓馬 | 非挿管患者のデクスメデトミジン投与による睡眠誘導のせん妄発生における有効性の検討 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 助教 | 髙谷 悠大 | 敗血症関連せん妄における腸内細菌叢由来トリプトファン代謝物の病態的意義の解明 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 特定研究員 | 山本 佳宏 | 食道扁平上皮癌に対するHSP90阻害剤をアンカードラッグとした分子標的治療法の開発 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 講師 | 角田 茂 | 超偏極13C-MRIを用いた高精度食道癌動的診断法の開発 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 講師 | 穴澤 貴行 | iPS細胞由来膵島細胞移植における抗原特異的安定型制御性T細胞による 免疫応答制御 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 助教 | 栢分 秀直 | サイズミスマッチを伴う肺移植におけるグラフト肺成長のメカニズムの探索 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 特定病院助教 | 小原 勉 | 子宮内膜由来のextracellular vesicleに着目した難治性着床障害の病態解明 | 950,000 | |
| 医学研究科 | 講師 | 飯塚 裕介 | 神経内分泌腫瘍に対するLu-177内用療法における吸収線量の推定と臨床成績の検討 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 特定病院助教 | 篠原 浩 | 溶血性連鎖球菌の薬剤耐性に及ぼすIntegrative conjugative elements (ICE)の特性解明 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 講師 | 渡邉 拓磨 | ロモソズマブのオッセオインテグレーションへの影響:骨粗鬆症ラットを用いた検討 | 800,000 | |
| 医学研究科 | 教授 | 緑川 光春 | シナプスにおける神経伝達物質放出を支えるナノ微細構造動態の解明 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 准教授 | 森瀬 譲二 | 糖鎖結合分子のハイスループットスクリーニングを可能とするLectinおよびヒトcDNA libraryの2種提示ファージの確立 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 特定准教授 | 依田 成玄 | 予後不良骨髄性腫瘍のPDXマウスモデルの作成と新規治療法の開発 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 教授 | 竹林 浩秀 | 予後不良骨髄性腫瘍のPDXマウスモデルの作成と新規治療法の開発 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 准教授 | 金 ?秀 | 病原細菌のユビキチンリガーゼを標的とする感染症治療薬の基盤創出 | 1,000,000 | |
| 医学研究科 | 講師 | Erik WALINDA | NF-κB経路を制御する直鎖状ユビキチン鎖の競合結合 | 1,000,000 | |
| 医学部附属病院 | 特定病院助教 | 安田 枝里子 | 絨毛膜下血腫における卵膜の組織障害・線維化の機序の探求と治療法の開発 | 1,000,000 | |
| 医学部附属病院 | 助教 | 石井 慧 | 腺組織を用いた乳腺再生組織量の増加を促進する正常微小環境の構築 | 1,000,000 | |
| 医学部附属病院 | 助教 | 三島 清香 | 顎矯正手術に伴う口腔咽頭の形態的・機能的評価と睡眠時無呼吸症候群に関する研究 | 950,000 | |
| 医学部附属病院 | 准教授 | 中川 俊作 | トランスオミクス解析による薬剤性腎障害の多層的な発症機構の理解と対処法の探索 | 900,000 | |
| 医学部附属病院 | 特定准教授 | 大橋 真也 | 消化器内視鏡検診NBI観察時に見られる食道褐色域に関する病因・病態の解明 | 1,000,000 | |
| 薬学研究科 | 講師 | 南條 毅 | N-ハロペプチドの学理構築と機能開拓 | 1,000,000 | |
| 生命科学研究科 | 准教授 | 菅田 浩司 | 多細胞集団のクオリティを最適化する分子機構の解明 | 1,000,000 | |
| 医生物学研究所 | 助教 | 佐藤 裕真 | 膜融合能亢進型麻疹ウイルスによる新規細胞侵入機構の解明 | 1,000,000 |
2. 研究成果公開支援
B. 国際会議開催助成
海外の学界との交流等、教育研究上の国際交流の促進に対する助成事業
3. 研究者交流支援
C. 在外研究助成
D.国際研究集会発表助成
4. 国際交流支援
E. 国際交流助成
| 所属部局 | 職名/学年 | 氏名 | 研究集会名 | 継続・新規 | 助成決定額 (円) |
成果 報告書 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学研究科 | 研究科長 | 立川 康人 | オランダ・アイントホーフェン工科大学・トゥエンテ大学との国際交流事業 「2025 International Hackathon」の開催 | 継続 | 2,000,000 |
社会との連携推進に対する助成事業
5. 社会連携支援